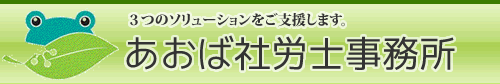ある日、ハローワークからの電話。
ハローワーク職員さん(以下HW):「先生が出されている求人に、応募者の方が来られているのですが」
私:「そうですか、それではよろしくお願いします」
HW:「その方から、求人票の学歴要件が大卒となっているので、高卒に下げてもらえませんかと話がきています」
私:「そうですか、いいですよ。求人票に記載してある仕事ができる能力があれば問題ないです」
HW:「ありがとうございます。ちょっと言いづらいのですが、あと3つ要望がありまして。
1つ目は、求人票に記載されている【事務仕事】は全くしたことがないので、どのような教育訓練制度があるのか知りたいと、
2つ目は【社労士の資格取得】を考えているので、どのような資格取得を支援する制度があるのか教えて欲しいと。
3つ目は、応募前に【職場見学】をお願いしたいそう。
可能でしょうか?」
私:「HWさん、求人票を作成するとき、ジョブ型ですから、実際にしてもらう“仕事内容”を詳細かつ具体的に記入することを求めていますよね」
HW:「おっしゃるとおりです」
私:「当社で求めている方は、求人票で募集した事務職という仕事をやっていただける方なのですが」
HW:「そうですよね」
私:「なぜ、職場見学を希望されているのですか」
HW:「快適に過ごせる職場かどうか、雰囲気がよいかどうか事前に見ておきたいそうです」
私:「……。当社は、彼女のリビングやスターバックスでもないですし、資格取得のための専門学校でもないのですが」
HW:「すみません、おっしゃる通りです」
近年、会社の責任はどんどん重くなり、お役所からの要求も多くなっているように感じる。
ジョブ型労働、同一労働同一賃金、安全配慮義務(職場環境配慮義務、健康配慮義務)、健康管理義務(労働契約法:企業は、社員が生命や身体の安全を確保する努力義務がある)、ハラスメント対策、メンタルヘルス、有給休暇取得の義務化……。
令和6年8月、失業率2.5%、新規求人倍率2.32倍(出典:厚労省令和6年10月1日Press Release)。
この数字の通り失業者は殆どおらず、人手不足、売り手市場である。喉の奥から手が出るほど、人が欲しい企業は山ほどあるはず。
しかし、企業も求職者も「そろそろお互い、よく考えようね」と私は言いたい。
「雰囲気が良いかどうか」、「過ごしやすいかどうか」が大事!それが確かに大事なことなのはわかる。
だって会社って、生活の中で結構長い時間を過ごす場所であるし。集中して仕事をしたり、学びや成長機会など様々なできごとがある場所だもの。
でも、条件検索より、まずは働くってことが先なのではないだろうかと思う。
職場のみんなと協力して働くことで「会社の雰囲気」ができるのであって、偉い誰かが勝手に会社の雰囲気をデザインしているわけではない。
一生懸命働いて、売上を上げ、会社への利益貢献がなければ、お給料が払えないと理解できないのか。
会社はあなたのお家のリビングでも、スターバックスでもないということも。
メタ認知的に解釈すると会社というものは実物として存在している訳ではなく、「物語であり虚構」である。
そこで働く社員、役員が会社という共通の物語を信じ、活動することで「会社という虚構は存在する」という。
かろうじて実在性を担保しているのは、会社法上で登記されたペーパーがあるだけ。ただの登記簿謄本という紙切れでしかない。
ハローワークインターネットサービスは、希望業界、会社の労働条件等を簡単に比較することができる。
給料、休日日数、残業時間数、転勤の有無などである。
「会社」の口コミ検索、ハローワークでの労働条件検索。「食べログ」で飲食店を探すように会社を探す、まるで会社を消費すべきサービスのように。
消費者として「失敗しないサービス(会社)」を探しても、決して失敗しないサービス(会社)は見つかることはないように思う。
なぜなら、会社は消費すべきサービスではなく、会社の存在を信じる社員、役員が、自ら創り出している場所であるからである。
「会社」を信じない人が、会社に来ても、ラテやフラペチーノどころか、「何もサービスのない空虚な場所」にしか見えないはずだ。